かなた「将棋の有用性について考えてみた」
どうもかなたです。
最近将棋にはまっております。

将棋自体は子供のころ祖父に教えてもらってやったことはありました。
最近ふと将棋をやりたくなってアプリでコンピューターと夜な夜な対戦しております(笑)
9×9マスという狭い盤上を「王将」、「飛車」、「角行」、「金将」、「銀将」、「桂馬」、「香車」、「歩兵」の8種類の計20駒でどう相手の王将を討ち取るかという目的のもと、様々な戦略や思惑が交錯させるなんとも奥深いものだと思います。
(チェスも似ているという認識ですが、やったことがなく、駒の動きを知っているので将棋を始めました)
コンピューターに余裕で負ける雑魚中の雑魚であるかなたですがこれから勉強して強くなっていこうと思っています。
ちなみにぴよ将棋っていう無料アプリで遊んでます。(公式へのリンクです)
なぜ将棋を学んでいこうと思うのかってとこなんですが、主な理由が以下
- 先読み力強化
- 形成判断能力強化
- ボケ防止
もくじ
先読み力強化
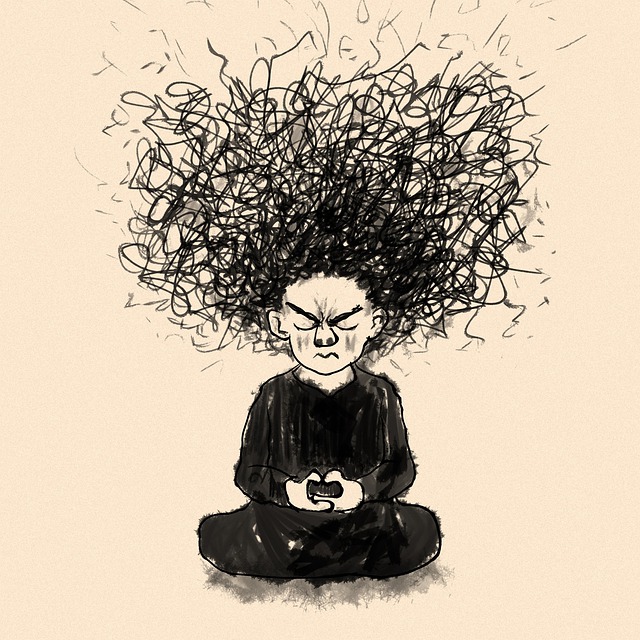
将棋はターン制で駒を動かすたびに絶対に手番が変わります。
ということは相手の考えが何手先まで読めるかが勝負の決め手になります。
極端に言えば終局まで相手の動きがわかってしまえば勝てるわけですよね。
「この駒をここに持ってきたからこうしたいんだな、じゃあこうしよう」といった風に相手の戦略を潰しつつ自分の攻めを通すことができなければなりません。
先読みの力は必須だと思います。
そしてこれを身に着けると絶対に日常生活にも役立つでしょう。
例えば「この人は何故これをしてるんだろう」と考え、理由がわかれば、それを防ぐこともできるし、手を差し伸べることもできるわけです。
それが楽しみながら勉強できると思えばやろうと思いますよね。
形成判断能力
これは簡単に言うと今の対局が優勢か劣勢か判断する能力ですね。
将棋は棋譜といって対局の記録を残します。それを見て対局を再現したり、振り返ったりします。
最近の将棋のゲームは(もちろん「ぴよ将棋」も)この振り返りまでできるようになっていて、形成判断のグラフまでつけてくれます。
これによってどこで優勢になったか、劣勢になったかが初心者にも一目瞭然です。
これを対局中に判断できるようになれば優勢を突き通すには、劣勢をひっくり返すには、等を考えられるようになります。
これは何の試合でもどんな場面においても言えますが、冷静に自分の置かれている状況や立場を理解できることは必要です。
それが分からないと今すべきことが見えてきません。
これも生きていく上で重要なファクターになり得るでしょう。
ボケ防止
最初に言った通りかなたは祖父から将棋を教えてもらいました。
祖父は何年も養護施設に入ってましたが、色んなことをメモして把握していたので看護士さんが「あれはどうでしたっけ」とか聞きにくるような存在でした。
そんな祖父を小さいながら誇らしいと思いました。
まあ将棋だけでこうなるとは言えないのですが、先読み、形成判断等考える事が多いことですので抑制にはなるんじゃないかと思います。
そういうかなたは最近もの忘れが気になり始めましたので勉強しつつ劣化しないよう努めていきたいと思います。
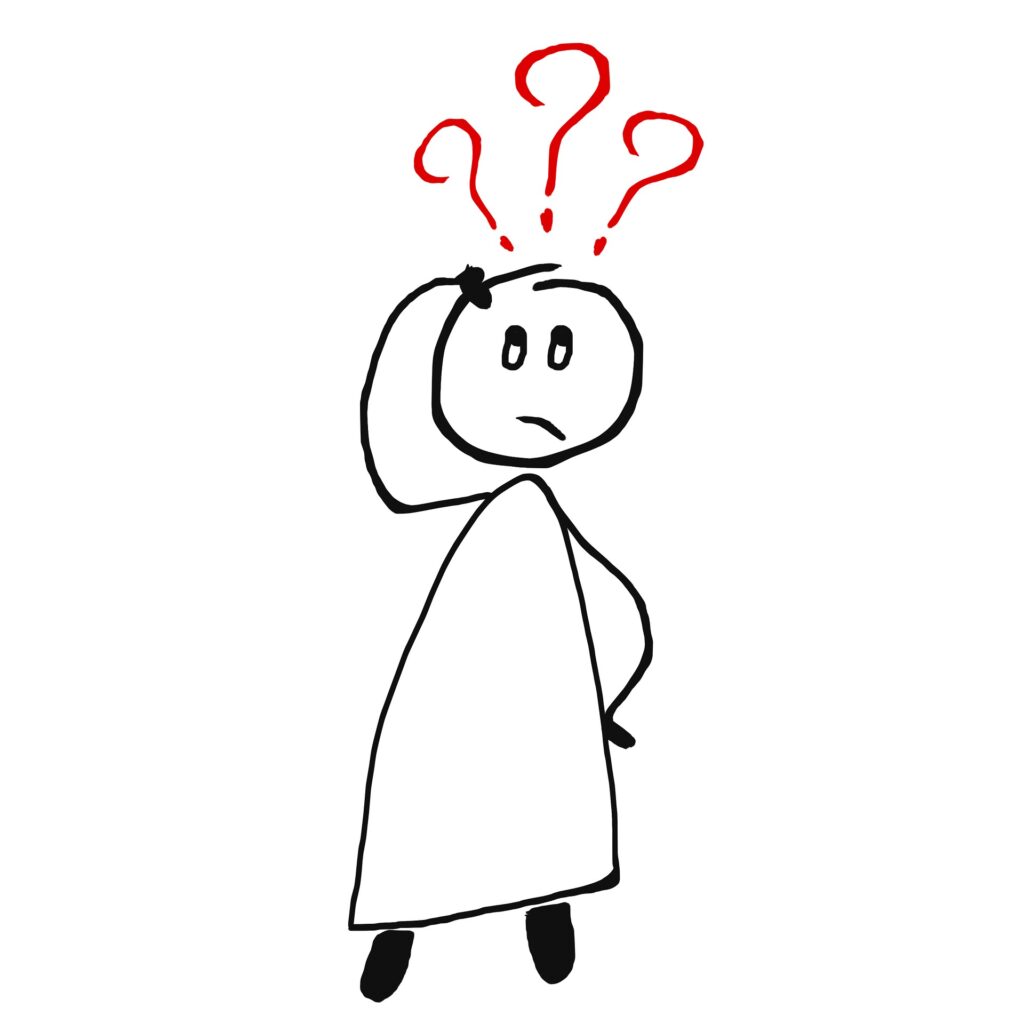
おわりに
色々言ってますがまだまだ勉強中です。
自分で動かした駒が邪魔で悶々とすることもしばしば(笑)
ただ身につくことは大いにありますし、もしかしたらこの道を志すことになるやもしれません。
どこに何のきっかけがあるか分かりませんからね。
人生楽しみましょう。
ブログランキング参加してみました↓を押してもらえるとやる気がみなぎります(かなたの)
保険や自己啓発的な事も書いてます。
お時間ありましたらぜひご覧ください。











